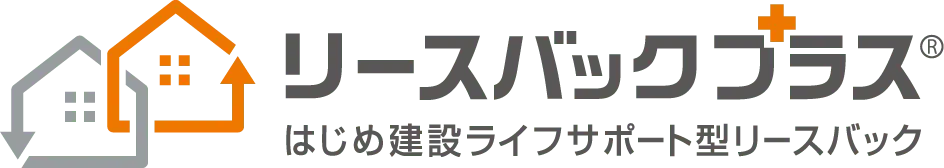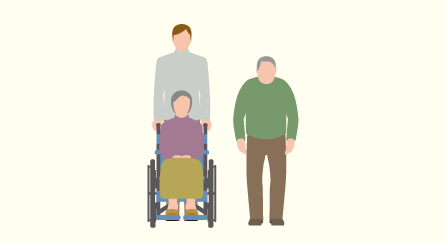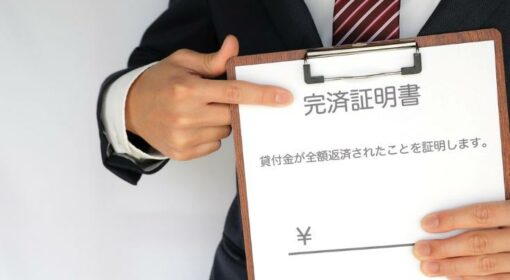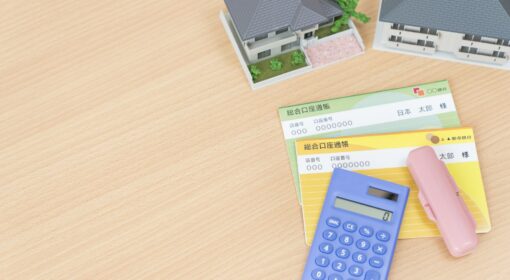住まいの維持費として大きいものに税金があります。持ち家を維持していくには、高額な税金を支払い続けなければなりません。
この税金が痛手になってしまっている人や、もう少し下げることができたらと思っている人も多いのではないでしょうか。今回は、持ち家にかかる税金の種類と特例措置、毎年の支払いの負担を軽減する方法を解説していきます。
思いもよらず多額の税金を払うことになってしまわないように気を付けたい注意点もご紹介するので参考にしてみてください。
持ち家を維持するためにかかる税金の種類
まず、持ち家を維持するために必要な2つの税金「固定資産税」「都市計画税」について、概要と計算方法を解説します。
毎年払わなければならない税金の負担を減らすためには、現在どんな種類の税金をいくら納めているのかを把握することが大切です。

固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して、市町村および東京23区が課税する税金で、持ち家を所有している期間中は毎年納める必要があります。
固定資産税は、2種類あり「土地にかかる固定資産税」と「建物にかかる固定資産税」です。
土地と建物の課税標準額を算定し、それぞれの税率をかけて出した「土地にかかる固定資産税」と「建物にかかる固定資産税」の合計が、固定資産税となります。
課税標準額とは、課税の対象になる基準となる金額で、不動産の場合は原則として固定資産課税台帳に登録された不動産価格のことを指します。
土地の固定資産税
土地の固定資産税=(課税標準税額)×(住宅用地特例)×1.4%(標準税率)
課税標準税額=(路線価)×土地の単位地積(1㎡)
土地の課税標準額は、3年に一度改定される路線価によって計算します。
路線価とは、道路に隣接する標準的な土地の単位地積(1㎡)あたりの価格で、国税庁のホームページで確認できます。
例えば、1㎡あたり30万円の土地を100㎡持っている場合は3,000万円と評価されます。更地であれば、この金額が課税標準額となりますが、住宅用地には「住宅用地の特例」が適用されます。
住宅幼稚の特例とは、住宅用地であれば、課税標準額に対して200㎡までは1/6、200㎡超の部分は1/3を乗じて課税標準額を計算する措置です。
上記の場合は200㎡以下ですので、500万円(3,000万×1/6)が課税標準額となります。
この価格の1.4%(標準税率)が固定資産税として徴収されるため、土地の固定資産税は500万円×1.4%=7万円と計算できます。
建物の固定資産税
建物の固定資産税=(課税標準税額)×1.4%(標準税率)
建物の課税標準税額は、固定資産税の納税通知書に記載されている課税明細書の価格(評価額)を確認します。例えば、500万円と記載されていれば、標準税率の1.4%を掛けた、7万円が徴収されます。
参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局
固定資産税の平均額と支払いについて
固定資産税は住宅の種類や構造、築年数、立地するエリアなどの条件によって変動しますが、おおよそ8~15万円とされています。あくまで平均値であるため、実際の税額は各市区町村から送付される納税通知書などを確認してください。
納税方法は、一括もしくは年4回の分割で行いますが、分割の場合の納付期限は自治体によって変わることがあります。
都市計画税
都市計画税=課税標準額{(土地の課税標準税額)+(建物の課税標準税額)}×最高0.3%(制限税率)
都市計画税についてはあまり耳馴染みがないかもしれません。
都市計画税とは、都市計画法によって定められた市街化区域内にある土地や建物などの不動産を毎年1月1日時点で所有している人に対して課税される税金です。
固定資産税とともに課税され、東京23区は都税に含まれています。
都市計画税の課税標準額は、各自治体が定める固定資産評価額となるため、固定資産税を計算した時の土地の課税標準税額と建物の課税標準税額を用います。
都市計画税にも「住宅用地の特例措置」があり、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準額×1/3、一般住宅用地(200㎡超の部分)は課税標準額×2/3となります。
上記のケースで計算すると下記の計算式で都市計画税が算出されます。
都市計画税=(土地の課税標準額1,000万円+家屋の評価額500万円)×0.3%(制限税率)
=1.5万円
参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局
持ち家の固定資産税の負担が減る軽減措置

固定資産税と都市計画税の2種類の税金に対して国は一定の軽減措置を設けていますが、特定の要件を満たす必要があります。そこで、固定資産税が減る軽減措置についてご紹介するので、マイホームが該当するかチェックしてみましょう。
土地の固定資産税を軽減できる制度
住宅用地特例措置
住宅用地特例措置は先述した計算式でも触れましたが、これは課税標準額を計算する際に土地の課税標準額を圧縮することで税金負担を軽減してくれる制度です。
住宅用地であれば、土地の固定資産税・都市計画税を1/6〜2/3まで軽減してくれます。所有する自宅の土地の広さと軽減率は下記のとおりです。
小規模住宅用地(200㎡までの土地)の課税標準額:固定資産税1/6、都市計画税1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準額:固定資産税1/3、都市計画税⅔
参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局
家屋の固定資産税を軽減できる制度
新築住宅
一定要件を満たしている新築住宅(一戸建て)は、固定資産税額の1/2が3年間、マンションの場合は5年間減税されます。
2018年3月31日までに建築された物件が対象でしたが、2018年に法律が改正され、2020年3月31日まで固定資産税の減額が延長されることになりました。この期限は、さらに2024年3月31日にまで延長されていていますので、しばらくは減税措置の恩恵を受けられます。
改修工事による減税
要件を満たす改修工事をすると省エネ改修に関する特例措置の対象となります。現在の状況に伴い、高齢者用にバリアフリー化した住宅や耐震改修を行った住宅、環境に配慮して省エネ改修を行った住宅など、政府が定めた一定の条件をクリアした住宅は、翌年度の家屋にかかる固定資産税が減税されます。
認定長期優良住宅
長期優良住宅とは、長期間・良好な状態で暮らすことができるように設計された住宅のことです。長期優良住宅に認定されると、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
長期優良住宅を新築した場合は5年間(新築中高層耐火建築物の場合は7年間)に渡り、家屋にかかる固定資産税額の1/2が減額されます。減額となるのは床面積が50㎡以上280㎡以下で、長期優良住宅と認定された住宅の、床面積120㎡までです。例えば、床面積200㎡の住宅であれば、120㎡までの固定資産税は1/2ですが、残りの80㎡は通常通りの課税となります。
◆軽減税率
| 課税対象 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
|---|---|---|---|
| 土地 | 住宅用地:~200㎡ | 課税標準額×1/6 | 課税標準額×1/3 |
| 住宅用地:200㎡超 | 課税標準額×1/3 | 課税標準額×2/3 | |
| 建物 | 戸建て | 税額×1/2(3年間) ※長期優良住宅は5年 | なし |
| マンション | 税額×1/2(5年間) ※長期優良住宅は7年 | ||
<省エネ改修に関する特例措置>
| 自己居住用家屋 | 一定の省エネ改修工事を行った場合、工事費用(上限250万円)の10%を所得税額から控除 | 適用期限:2023年12月31日 |
|---|
<バリアフリー改修に関する特例措置>
| 自己居住用家屋 | 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事費用の一定額を所得税額から控除 | 適用期限:2023年12月31日 |
|---|
要注意!持ち家の固定資産税の負担増加の可能性
ここまで固定資産税の負担を減らす制度について説明してきましたが、逆に税負担が増加してしまう可能性もあります。うっかり忘れていて負担が増えてしまったということのないように、注意すべきポイントを解説します。

住宅の取り壊し
住宅地として軽減措置を受けるためには、1月1日時点で住宅が建っていなければなりません。そのため、年末に取り壊しを行ってしまうと、住宅用地とみなされなくなり、軽減措置の対象外となってしまいます。
その場合、固定資産税が3〜6倍に膨れ上がってしまう危険性があるため、取り壊しを考えている方は1月2日以降に取り壊しを行いましょう。
空き家の放置
2015年より、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」という法律が施行されました。空き家の増加に伴い制定されたもので、以下の物件が対象となります。
- 建物の倒壊や保安上の危険がある物件
- 衛生的に問題がある物件(ゴミ屋敷など)
- 管理がされておらず景観を損なっている物件
- その他放置することによって周辺の生活環境が脅かされる物件
この法律により、市町村から「特定空き家等」の勧告を受けると、住宅用地の特例の対象外となってしまうため固定資産税が上がってしまいます。
持ち家はしっかり管理して、住宅として認めてもらえるようにしておきましょう。別荘や家を2つ持っている方は、日々の管理を怠らないように、工夫して管理することが重要です。
家屋調査の拒否
家屋調査とは、固定資産税の算出をするために行われる調査のことで、実際に家屋に立ち入って、用いられている資材や設備など資産価値を調査します。
屋内への立ち入りを避けたい場合は、書類の提出などで済ませられることもありますが、実物の調査が行えず正確な評価ができないため、本来より固定資産税が高くなる可能性があります。税負担の増加を防ぐには、できる限り調査に協力をすることをおすすめします。
なお、正当な理由がない家屋調査の拒否や、提出した資料に虚偽の記載があった場合は罰則もあります。
「持ち家の税負担を減らすために」
持ち家の維持にかかる税金は固定資産税と都市計画税の2種類があり、税率の計算方法や軽減措置を受ける要件を知っておくことが大切です。持ち家を保有している方、これから建設・購入予定の方は、減税のための条件を確認し、減免措置を受けられるように申請を忘れないようにしましょう。
一方で、持ち家の税負担を軽くする方法の一つに家を売却したのちも住み続けるという「リースバック」という仕組みがあります。リースバックは、所有権が売却したリース会社に移り、家賃が相場よりも高くなりやすいといったデメリットがあります。しかし、所有権がなくなることにより固定資産税が不要となり、これまでと同じように自宅に住み続けられます。まとまったお金を作ることができ、なおかつ税負担を軽減できる方法として注目が集まっています。
リースバックに関してはこちらの記事を参考にしてみてください。
[関連リンク]
リースバックの仕組みとは?メリット・デメリットや流れ、注意点をわかりやすく解説
一建設株式会社が提供する「リースバックプラス+」では他社にはない仕組みを取り入れ、様々なニーズに応えることができる2つのプランを用意しています。
売却後に賃貸契約を更新していくことが可能な「標準プラン」は、賃貸として住んだ長さに応じて再購入時の価格が下がる仕組みを、業界で初めて導入しています。最短でも10年間、再購入価格が下がっていきます。また賃貸3年目以降は新築物件への引っ越しも可能という、こちらも業界初の試みです。
一方、比較的早期の買い戻しを計画している方や一時的な資金調達の方には「定期プラン」が向いています。こちらのプランでは、最大1年間の賃料が0円(以降は定期期間に応じて賃料設定)になる「賃料優遇タイプ」と、定期借家契約の期間を2年~5年と限定することで買戻価格が売却価格と同額(諸経費が別途かかります)となる「買戻優遇タイプ」があります。
また両プラン共通して、より快適で安心な生活のためのサポートサービスなども利用可能です。
このように、一建設株式会社の「リースバックプラス+」には、将来設計に合わせた充実のプランが用意されています。
リースバックをご利用になるなら、選べるプランと充実の特典が魅力の「リースバックプラス+」をご検討ください。

[関連リンク]