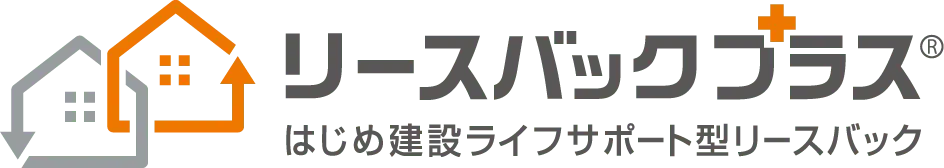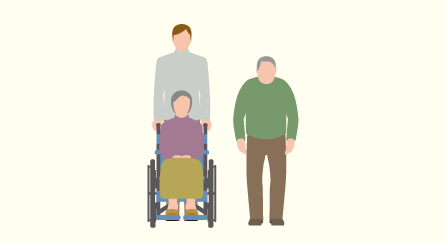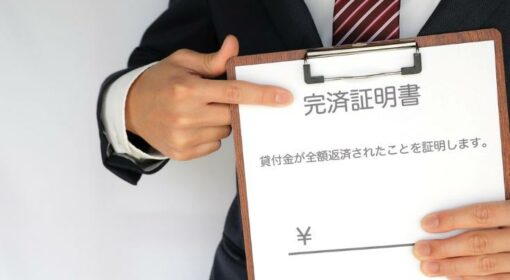超高齢社会へ突入してから年数の経過している日本では、夫の介護を同世代の妻が行う老々介護など、さまざまな問題が生じています。特に多くの方が抱えているのが、介護にかかるお金に関する悩みです。
本記事では、親の介護にかかる必要費用の平均や自己負担額の目安、使えるお金がないときの対策方法などを解説します。公的機関や民間会社が提供する制度もご紹介しますので、現在介護にお悩みの方や将来の介護に不安のある方は、ぜひ参考にしてください。
INDEX
親の介護にかかる費用は?お金はいくら必要なの?
親の介護は長期間におよぶことも多く、精神的なストレスだけでなく金銭的な負担も大きくなります。こちらでは、親の介護に必要なお金の目安をご紹介します。

介護費用の自己負担額は1~3割
母親や父親の介護が必要になった場合、家族で身の回りの介護をすべて行うこともできますが、サラリーマンとして仕事をしていたり実家を離れていたりすると簡単ではありません。そんなときは、各種介護保険サービスを利用するのが一般的です。
介護保険サービスにはさまざまな種類があり、有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、サービス付き高齢者向け住宅などの介護施設に入所したり、自宅で訪問介護やデイサービスなどを受けたりする方法があります。入居一時金や施設の利用料など、選択した方法や施設によって金額が異なるため、不安があればFP(ファイナンシャルプランナー)やケアマネジャーに相談すると良いでしょう。
介護保険サービスを利用する場合、介護保険の対象となる費用の負担割合は1~3割で、利用者本人の所得や65歳以上の方の世帯人数によって変わります。まず、利用者が要支援や要介護者に認定されると、自己負担の割合は1割になるのが基本です。2割負担になるのは、「合計所得金額が220万円以上かつ、年金とその他の収入の合計金額が240万円以上340万円未満(2人以上の世帯の場合、346万円以上463万円未満)」の方です。「合計所得金額が220万円以上かつ、年金とその他の収入の合計金額が340万円以上(2人以上の世帯では、463万円以上)」の方は、3割負担となります。ただし、一定金額を超えた分や、介護保険の対象とならない食費などは、全額負担となるため注意しましょう。
親の介護にかかる費用やお金
公益財団法人生命保険文化センターの「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護に要した費用は、一時費用として平均69万円、月々の費用が平均7.8万円とされています。
在宅介護の場合は4.6万円、施設介護の場合は11.8万円が平均です。要支援よりも要介護、要介護でも数字が大きいほど介護費用が高くなる傾向にあります。
介護期間の平均である54.5カ月(4年7カ月)で計算した場合、介護費はおおよそ平均500万円程度かかります。ただし、あくまで平均値をもとにした算出のため、実際の費用はケースバイケースです。親の資産や自分が捻出できる時間、お金を考慮したうえで、どのサービスを受けるか判断しましょう。
参考:
平成30年度 「生命保険に関する全国実態調査」|公益財団法人生命保険文化センター
医療にかかる費用もチェック
高齢になると病気や怪我の治療にかかる医療費が高くなる傾向があります。介護をするようになると医療も必要になるケースが多いので注意しましょう。2020年に公開された厚生労働白書では1年間にかかる平均的な医療費は65歳以上で733,700円、70歳以上で807,100円、75歳以上で902,000円です。
また、継続的な入院が必要になると医療費は高くなります。入院するときには差額ベッド代、食事代、おむつ代などの負担があります。受ける治療の内容によっては手術費用や技術料などの負担もあります。投薬を伴う治療の場合には薬代も高くなるのが一般的です。平均的には自己負担額として入院のときに20万円程度、入院1日あたり23,000円程度が必要になります。
参考:
医療保険に関する基礎資料~平成30年度の医療費等の状況~| 厚生労働省保険局調査課
親の介護費用って、誰がお金を払うもの?

親の介護には、介護サービスの月額費用だけでもある程度のお金が必要です。これを子どもや兄弟姉妹間で賄うとなると、大きな負担につながります。親の介護に必要なお金は、誰が準備すべきなのでしょうか。
親の介護費用は、本人や夫婦の年金や貯蓄などから捻出して支払うのが基本です。同居しておらず家を購入して住宅ローンを支払っていたり、老後の資金を貯蓄していたりと、子どもには子どもの生活があるため、親の介護費用を負担すると家計が苦しくなるおそれがあります。
ただし、何らかの理由で現役時代に十分な貯蓄を作れず、年金だけでは介護費を賄えないケースも少なくありません。そのような場合は、家族で相談して子どもが負担したり、公的機関や民間会社の提供する制度や商品を活用したりして介護サービスを受けることになります。具体的には、リースバックやリバースモーゲージ、マイホーム借り上げ制度などが注目されています。
親の介護費用に活用したい制度
高額介護サービス費を利用する
介護費用の負担を軽減するには、高額介護サービス制度を利用するのも良いでしょう。高額介護サービス費とは、1カ月の介護費の負担額が限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の一般的な所得の場合、負担上限額は44,000円となっています。基準を超えて負担しているのであれば、払い戻しを受けられる可能性があるため、一度確認してみましょう。
参考:
高額介護サービス費の負担限度額が変わります| 厚生労働省
生活福祉資金貸付制度を利用する
生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯や認知症などの障害を持った方がいる世帯、介護が必要な高齢者がいる世帯を対象とした貸付制度です。無利子もしくは低利子で融資を受けられるため、生活困窮者のセーフティネットとして役割を果たしています。ただし、通常の貸付と比較すると負担は軽減されるものの、貸付のため返済が必要な点に注意しましょう。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費は低所得者の介護に利用可能な、居住費(滞在費)・食費の補助を受けられる制度です。所得と預貯金の状況に応じて、第1段階・第2段階、第3(1)段階、第3(2)段階の4段階に区分されます。居住費はこの段階と居住している部屋の種類によって負担限度額が決まります。食費は段階によって一義的に上限が決まる仕組みです。
特定入所者介護サービス費は特別養護老人ホームなどの公的な介護施設に入所しているときにだけ適用可能です。世帯全員が住民税非課税になっている場合には対象になる可能性があるので、お住まいの市区町村に問い合わせてみましょう。

利用者負担の軽減制度
国や都道府県、市区町村などによって公費で介護負担を軽減する制度もありますが、社会福祉法人などの協力による利用者負担を軽減する制度もあります。軽減制度を設けている社会福祉法人の介護施設などを利用した場合に適用できる可能性があるので、利用する介護施設を検討するときには念頭に置いておきましょう。
利用者負担の軽減制度は市区町村の窓口で申請をすることで負担を減らせる仕組みになっています。利用者負担の4分の1、老齢福祉年金受給者は2分の1が軽減される制度です。利用できる施設やサービスは限られますが、介護費の削減には効果的です。
税金の控除
介護費の支払いが直接的に減るわけではありませんが、税金の控除を適用することで支出をトータルとして減らすことが可能です。介護保険料は社会保険料控除の対象なので所得税も住民税も減らせるでしょう。
また、介護サービスの利用料のうちで医療に関連する内容については医療費控除の対象になります。要介護認定を受けて医師による治療を受けている場合には、「おむつ使用証明書」を発行してもらうことでおむつ代も医療費控除の対象にすることが可能です。訪問看護や訪問リハビリテーションなども医療として位置づけられているので医療費控除の対象になります。
親の介護費用に活用したい制度

年金や預貯金で介護費用を賄う場合、金額には限度があり、使えるお金がなくなってしまう可能性があります。こちらでは、親の介護でお金が足りなくなったときの対策をお伝えします。
支払える額をベースにケアプランを作成する
親の介護費用に不安がある場合は、家計の状況を考慮して、毎月支払える金額をもとにケアマネジャーにケアプランを作成してもらうのがおすすめです。ケアマネジャーは、プランの見直しを行う「モニタリング」業務を毎月行うことになっているため、その際に費用面の相談をしましょう。ケアプランを作成する場合は、おむつ代や介護食代、理美容代など、介護保険の対象とならない費用も考慮することが大切です。
リバースモーゲージを利用する
リバースモーゲージは主に高齢者向けに提供されているサービスで、持ち家を担保としてお金を借りることができます。担保にするだけなので自宅に住み続けることが可能です。持ち家の評価額に応じて借り入れ可能な限度額が設定される仕組みになっています。一括して受け取ることも、年金のように毎月受け取ることも可能です。
また、リバースモーゲージではカードローンなどとは違って、元本を毎月返済する必要はありません。持ち家を最終的には金融機関に渡して売却することにより、貸付金を回収することが想定されているからです。利息分だけの支払いか、完全に返済がない場合もあります。貸付金は、老後の資金としての用途に限られることが多いですが、介護費用には使えるのが一般的です。
[関連リンク]
リバースモーゲージとは?やばい?仕組み・メリットなどをわかりやすく解説
持ち家をリースバックする
実家など持ち家がある場合、リースバックをして資金を確保するという手もあります。リースバックとは自宅を売却しつつ賃貸契約を結ぶことで、同じ家に住み続けられるサービスです。最近では、相続対策のひとつとしてリースバックを利用することもあります。自宅を手放すことになるものの、まとまった資金を得られ、引っ越しも必要ありません。
ライフスタイルに適したリースバック商品をお探しの方には、一建設の「リースバックプラス」をおすすめします。ご家族の将来設計に応じて、「標準プラン」「定期プラン」の2プランをご用意しています。介護目的での資金調達も、お気軽にお問い合わせください。
[関連リンク]
リースバックとリバースモーゲージの違いとは?仕組みや特徴を徹底比較
生活保護を申請する
資金に余裕がなく、日常生活に困窮するようなケースでは、生活保護の利用も検討すると良いでしょう。ただし、生活保護を申請できるのは、十分な資産がなく生活をサポートしてくれる親族がいない場合に限られています。子どもに経済的な余裕があると、親が生活保護を受けられないケースもあります。
親の介護費用でトラブルにならないようにするには?

将来的に親の介護が必要になることを想定して、トラブル対策をしておくのは大切です。介護費用のトラブルにならないようにするにはどうしたら良いのでしょうか。今からできる対策をご紹介します。
介護方針をあらかじめ話しておく
親子で介護方針について相談しておくとトラブルが少なくなります。自宅介護をして欲しい、施設に入りたいなどといった親の希望を聞いてみるのがまず大切です。介護が必要になった時点で子としては何をするのが親にとってベストなのかがわかります。その上で、介護に必要な費用を概算して、誰がいくら負担するのか、介護施設に通う場合には送迎はどうするのかといった議論をしましょう。
自宅介護の場合にはバリアフリーのリフォームが必要になる場合もあります。訪問介護や訪問看護を利用するのかどうかも話をして、費用負担のあり方を明確にしておきましょう。
親の資産や年金について確認しておく
親の介護が必要になったときに介護方針が明確になっていて資金の負担についての相談が済んでいたとしても、親の貯蓄額や年金額では足りない場合があります。トラブルを避けるためには、親の資産や年金について確認しておくことが大切です。親は必ずしも自分の資産や年金について詳しく把握しているとは限りません。自分で払えると言っておきながら、実は全然足りないということもあり得ます。
介護方針を親に相談するときに、親の資産状況も教えてもらいましょう。そして、無理のない生活ができるように資金分担の方針を決めるのが良い方法です。
介護施設や介護サービスを調べておく
親の介護を見越して介護施設や介護サービスについて調べるのも重要です。施設によって他にはないサービスをしている代わりに、介護保険が適用できないといった場合もあります。公的施設に比べると民間施設の方が利用料金は高い傾向がありますが、サービスが充実していることもよくあります。具体的なサービス内容と費用がわかると親との相談も進みやすくなります。
親が介護施設に入所したいか、自宅で介護サービスを受けたいかによって調査対象も変わります。まずは簡単に親と相談をして方針を定めてから利用できる介護施設や介護サービスを確認しましょう。
親の介護費用を抑える施設選びのポイント
親を介護施設に入居させたいけれど、なるべく経費を抑えたい場合は、施設の選定時に以下の要点を把握することが重要です。

費用を抑えるための施設選びにおいて注目すべきポイントは、以下の4つです。
- 公的施設の利用
- 立地条件の柔軟化
- 築年数の古い施設の選択
- 空き部屋の多い施設の選択
それぞれのポイントについて説明します。
公的な施設を利用する
社会福祉法人などが運営する「介護保険施設」であれば、月々の利用料の支払いのみで初期費用がかからないため、費用を抑えることができます。介護保険施設には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院(療養病床)、ケアハウスなどがあります。各施設の特性や提供されるサービスを詳しく調べて、親に適した施設を選択しましょう。
立地条件を緩める
介護施設も、住宅と同じように、良好な立地条件にある場合は家賃が高くなる傾向があります。一方で、公共交通機関の利用でアクセスしづらい立地にある施設は、費用を抑えられる場合があります。例えば、都心から少し離れた場所や、最寄り駅から距離のある場所に立地する施設を探してみると、比較的費用を抑えられるかもしれません。
築年数が古いものを選ぶ
築年数が経過した老人ホームの場合も、一般の住宅と同じように費用を抑えることが可能です。また、新しく開設されたばかりの施設は、スタッフの運営がまだ整備されていない可能性も考えられます。そのため、新築や築浅などの建物条件などの要素にこだわり過ぎる必要はないと言えるでしょう。
空きの多い施設を選ぶ
空きの多い介護施設では、時折、空室を埋めるために費用を割引していることがあります。この状況は、施設自体に何らかの問題があるわけではなく、ご逝去や退去が重なったケースなども考えられます。一時的な措置が取られていることもあるため、気になっている施設があれば、早めに問い合わせてみましょう。
親の介護費用で悩んだ時の相談窓口

「親の介護にかかる費用について、どこに相談すれば良いのか?」と悩んでいる人は多く存在します。親の介護で悩みがある場合は、以下の場所で適切なアドバイスを得ることができるので、相談してみましょう。
- 地域包括支援センター
- 地方自治体および社会福祉協議会
- 介護サイトの無料相談
それぞれの特徴やメリットを見てみましょう。
相談窓口紹介① 地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者が安心して生活できるように地域でサポートする施設です。全国の市町村に設けられており、その数は5,404か所にのぼります(令和4年4月末時点)。保健師や社会福祉士らの専門家が各センターに配置されており、高齢者からの相談に応じています。介護に関する問題を抱える場合も、地域包括支援センターにまず相談することをおすすめします。
相談窓口紹介② 市区町村などの自治体
多くの地方自治体や社会福祉協議会では、高齢者向けの相談窓口が設けられており、自治体の公式サイトや代表電話を通じて連絡し、相談を行うことができます。例えば、「東京都 高齢者 相談窓口」と検索すると、都庁の相談・窓口案内/高齢者のページが表示され、相談専用電話や問い合わせの受付時間を確認することができます。
相談窓口紹介③ 介護サイトの無料相談
介護に関する情報を得る手段として、無料の相談サービスを利用することもおすすめです。もし介護施設についての情報を求めているなら、専門のウェブサイトを活用することができます。例えば、「ケアスル介護」というサイトでは、介護施設の概要や入居に関する詳細な情報について、事前に無料の相談を行うことができます。多忙な日常に追われる方々も、手軽に相談できる介護サイトをぜひ活用してみましょう。
参考:理想の介護施設・有料老人ホームが見つかる | ケアスル 介護
「親の介護でお金がないときは各種制度を利用しよう」
今回は、親の介護でお金に困った場合の対策やおすすめの制度をご紹介しました。現代の高齢者は元気な方が多いものの、いつ介護が必要になるかわかりません。特に、「介護は長男・長女がするもの」というイメージを持っている方も多く、突然対応を迫られて兄弟姉妹間でトラブルに発展することもあります。
介護費用を捻出できない場合は、まず地域包括支援センターやケアマネジャーに相談をし、費用負担の少ない介護施設への入居や国や自治体が提供している制度を活用しましょう 。
現在介護に困っていない場合でも、万が一に備えて家族で話し合い、対策しておくことが大切です。
リースバックなら、一建設の「リースバックプラス」へ
親の介護費用を調達する際、持ち家がある場合はリースバックを活用するのも1つの方法です。特に一建設の「リースバックプラス」では家庭の事情に応じたプランとサービス内容を選べる点でおすすめです。リースバックプラス「標準プラン」では親の介護のための資金は必要だけれど、将来的には親の家に子が住みたいといったときに適しています。標準プランは賃貸で暮らしている間に買い戻し価格が下がっていく仕組みになっています。
また、リースバックをしたときには家賃の負担が悩みになる場合もあります。リースバックプラスでは、家賃を最大で50%も減額できるサービスを提供しています。更新料なども一切不要で利用しやすいリースバックなのでぜひ検討してみてください。