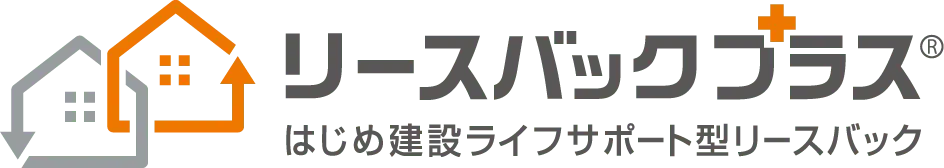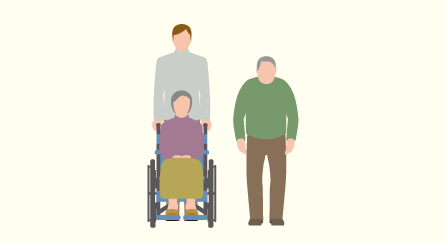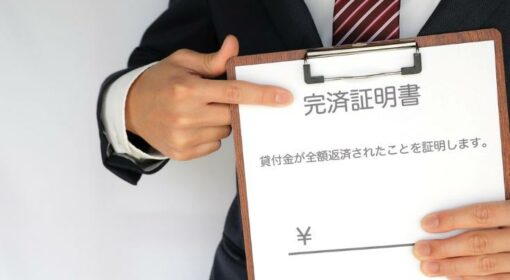「老後2,000万円問題」が話題になったことが記憶に新しい方も多いでしょう。
老後資金への不安な話題を耳にすると、「自分の老後にはいくら資金が必要なのか」気になりますよね。
とはいえ、老後資金を準備する必要性はわかっていても、どうやって貯めればいいのかわからないという方も多いものです。
この記事では、老後資金の目安額やその貯め方をわかりやすく解説します。
INDEX
老後資金は年金のみだと2,000万円不足する?

老後資金が年金だけでは2,000万円不足するといわれる「老後2,000万円問題」を耳にした方も多いでしょう。
これは、2019年に金融庁が公表した高齢社会の資産形成についての報告書が発端です。
この報告書では、老後30年間で必要な資金を算出したところ、年金受給額だけでは2,000万円が不足するという試算がされています。
この試算では夫65歳以上・妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯で生活費が毎月5.5万円不足すると算出され、老後20年~30年では不足額が2,000万円に上るとされています。
不足額自体はあくまでモデルケースでの算出であり、世帯ごとに家族構成や収入・支出が異なるため一概に2,000万円不足するわけではありません。
しかし、平均寿命が高齢化するにつれ、退職金や年金の受給額は減少傾向にあります。
老後に資金が不足する可能性は十分にあるため、一度自分の老後資金をシミュレーションしておくと良いでしょう。
老後に必要な資金の計算方法

将来必要な老後資金を算出するための基本的な計算式は以下のとおりです。
必要な老後資金 = (老後の生活費 – 収入) × (90歳 – 退職予定年齢)
この計算式では、退職後に必要な生活費から公的年金などの収入を差し引いた金額を求め、その赤字額に退職予定年齢から90歳(仮定した年数)までの年数を乗じます。
年金の受け取り額の計算方法
老後は、年金が主な収入源となります。
このため自分にとって必要な老後資金を計算するには、将来自分がいくら年金をもらえるのか、その金額の目安を知る必要があります。
日本の年金制度は、「国民年金」と「厚生年金」の2階建てとなっています。
国民年金は20歳以上60歳未満の全員が加入するもので、公務員や会社員であれば、それに厚生年金が上乗せされる仕組みです。
年金の受取額は国民年金と厚生年金で計算方法が異なります。国民年金は、以下の方法で算出できます。
年金受給額(年額)=777,800円×(保険料納付済み月数+免除期間)÷480月
480月(40年)欠かさずに保険料を納めていた場合、満額である777,800円が支給されます。
ただし、満額の金額については、物価変動などによって毎年見直されるので注意が必要です。
また、保険料の免除期間がある場合は、以下のように免除割合に応じて免除期間を計算します。
- 全額免除:免除月数×4/8
- 4分の1免除:納付月数×5/8
- 半額免除:納付月数×6/8
- 4分の3免除:納付月数7/8
国民年金には「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」≧10年という受給要件があり、上記を満たさなければ受給できません。
厚生年金は、納付期間だけでなく、収入金額によっても受け取れる額が異なります。
平均月収毎の大まかな目安は、次のとおりです。
| 平均月収 | 厚生年金納付年数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
| 20万円 | 13万円 | 27万円 | 41万円 | 55万円 |
| 30万円 | 20万円 | 41万円 | 62万円 | 83万円 |
| 40万円 | 27万円 | 55万円 | 83万円 | 110万円 |
| 50万円 | 34万円 | 69万円 | 103万円 | 138万円 |
厚生年金の受給額の計算は複雑で、要件によっても大きく変動します。
正確な年金額を知りたい場合は、「年金定期便」やインターネットで年金情報を確認できる「ねんきんネット」などを活用して、自分の年金額を確認するとよいでしょう。
老後の平均収入
総務省統計局が発表した2021年家計調査によると、65歳以上の年金と社会保障給付を合わせた収入額の平均は月額236,576円でした。
これは夫婦ともに無職の2人家庭における金額です。
個人年金保険や企業型確定拠出年金に加入していた場合には上乗せがありますが、国民年金や厚生年金にしか加入していなかった場合には月216,000円程度が平均値となっています。
【ケース別】実際に必要な老後資金はいくら?
それでは、実際に将来必要となる老後資金は一体いくらぐらいなのでしょうか?
ここからは、以下のモデルケース別に必要な老後資金を解説します。
- 独身・一人暮らしの場合
- 夫婦ふたり暮らしの場合
- 持ち家がある場合
- 賃貸住まいの場合
独身・一人暮らしの場合
65歳以上のひとり暮らしの場合の費用の目安は以下の通りです。
- 収入125,423円
- 消費支出月平均額:133,146円
毎月の赤字:7,723円
| 収入・支出 | 費用 |
|---|---|
| 収入 | 125,423円 |
| 消費支出月平均額 | 133,146円 |
| 毎月の赤字 | 7,723円 |
仮に、他の費用が夫婦同様の場合の老後30年間で必要な資金は、以下の通りです。
- 生活費不足分:280万円
- 家の維持費やリフォーム費用:200万円
- 自動車購入費用:200万円
- ライフイベントに関する費用(お祝い金など):100万円
- 医療費:300万円
- 葬祭費:200万円
- 趣味や娯楽費:月2.5万円×12ヵ月×30年間=900万円
トータルで2,180万円が必要となる計算です。
| 用途分類 | 費用 |
|---|---|
| 生活費不足分 | 280万円 |
| 家の維持費やリフォーム費用 | 200万円 |
| 自動車購入費用 | 200万円 |
| ライフイベントに関する費用(お祝い金など) | 100万円 |
| 医療費 | 300万円 |
| 趣味や娯楽費 | 月2.5万円×12ヵ月×30年間=900万円 |
夫婦ふたり暮らしの場合
2021年家計調査によると、65歳以上の無職世帯での可処分所得は205,911円です。
それに対し、支出額合計は224,436円となっています。
しかし、これは消費生活費のみの金額であり、家のリフォームやライフイベントに関わる費用・医療費、趣味など老後を充実させるための費用などは含まれていません。
仮に、以下のような費用がかかるとした場合、その計算は以下のとおりです。

- 生活費不足分:670万円
- 家の維持費やリフォーム費用:200万円
- 自動車購入費用:200万円
- ライフイベントに関する費用(お祝い金など):100万円
- 医療費:300万円×2人=600万円
- 葬祭費:200万円×2人=400万円
- 趣味や娯楽費:月5万円×12ヵ月×30年間=1,800万円
合計:3,970万円
このように、夫婦2人暮らしの場合は、年金などの収入以外で4,000万円程度の費用が必要になるといえます。
| 用途分類 | 費用 |
|---|---|
| 生活費不足分 | 670万円 |
| 家の維持費やリフォーム費用 | 200万円 |
| 自動車購入費用 | 200万円 |
| ライフイベントに関する費用(お祝い金など) | 100万円 |
| 医療費 | 600万円 |
| 葬祭費 | 400万円 |
| 趣味や娯楽費 | 1,800万円 |
| 合計 | 3,970万円 |
持ち家がある場合
自宅が賃貸か持ち家かによっても、老後資金の金額は変わってきます。
2021年家計調査によると、世帯主が65歳以上で2人以上いる高齢世帯のうち、91.7%は持ち家を所有しているというデータがあります。
つまり夫婦2人暮らしの高齢世帯は、9割以上が持ち家ということです。
持ち家の場合は、住宅ローンの完済後は住居にかかる費用が賃貸に比べて少なくなります。
マンションは、修繕積立金という形で負担するため維持費用を計算しやすいですが、戸建ては各々のタイミングで修繕・メンテナンス費用が必要となります。上記のモデルケース「夫婦ふたり暮らしの場合」の計算どおり「家の維持費やリフォーム費用」として200万円ほどを準備しておくと安心です。
賃貸住まいの場合
夫婦2人暮らしの高齢世帯は9割以上が持ち家を所有しているため、上記のモデルケース「夫婦ふたり暮らしの場合」は、ほぼ持ち家の方のデータが反映されています。
賃貸の場合は家賃の負担があるため、上記データより支出が大きくなりがちです。
たとえば、夫婦2人で家賃6万円の物件に住み、老後25年間住むと仮定した場合、少なくとも6万円×25年(300ヵ月)=1,800万円は住居にかかる費用として必要になります。
そもそも老後資金が必要な理由とは?
そもそも老後資金が必要な理由は、主に以下の3つが要因として挙げられます。
- 年金以外の収入がなくなるため
- 医療費や介護費の出費に備えるため
- 死後に清算する費用があるため

年金以外の収入がなくなるため
多くの企業や公共機関では、労働者が60歳で退職する「定年制」が導入されています。
このため退職後は給与所得がなくなり、公的年金しか収入がない状態になるのが一般的です。
近年では、定年退職の年齢を65歳まで引き上げる継続雇用制度を導入するなどして、60歳以上の労働者が働き続ける職場も増えていますが、給与は大幅に下がることが多いようです
医療費や介護費の出費に備えるため
これまで健康的な生活を送ってきた方も、加齢とともに医療・介護のサービスを必要とする可能性は高いです。
医療費の自己負担は、基本的に75歳以上の方で1割、70~74歳の方で2割となっています(現役並みの所得のある方は3割)。
現役と比べて自己負担の割合は減るものの、入院や手術が必要な病気にかかれば大きな出費が予想されます。
また、介護サービスが必要となれば、さらに大きな出費となるでしょう。
死後に清算する費用があるため
死後は葬式をおこなったり墓地を購入したりするための資金が必要です。
また、遺品整理にもお金がかかるほか、亡くなる直前に入院していた方は、入院費用の支払いも考慮しなければなりません。
老後資金にはこれらの死後に必要な資金も含まれるため、遺族のためにも生きている間に準備をしておくと安心です。
老後資金の主な内訳
老後資金と一口にいっても、その用途はさまざまです。
何にいくらくらい必要なのか理解することは、より具体的に老後資金の必要金額を計算するのに役立ちます。
老後資金の主な内訳は以下のとおりです。
- 生活費
- レジャー費
- お祝い金
- リフォーム代
- 医療費
- 介護費
- 葬儀代
ここからは、7種類の費用がどんな時にどれくらい必要になるのかを紹介します。
生活費
老後資金の中でももっとも大きな割合を占めるのが生活費です。
2021年家計調査の項目では、消費支出のなかでも食費や以下のような費用が生活費に該当するといえます。
- 家具や家事用品
- 通信費
- 衣服
- 交通費
| 用途分類 | 支出額 |
|---|---|
| 食費 | 65,789円 |
| 住居 | 16,498円 |
| 光熱・水道 | 19,496円 |
| 家具・家事用品 | 10,434円 |
| 被服・履物 | 5,041円 |
| 交通・通信 | 25,232円 |
参考元:総務省統計局 家計調査年報年報(家計収支編)2021年(令和3年))
レジャー費
充実した老後を送るには、趣味や教養・レジャーなどの費用も必要です。
生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(令和元年度)によると、ゆとりある老後に必要な生活費は月額平均36万円となります。
総務省の2021年家計調査における65歳以上夫婦のみの世帯の月の支出額は約22万円のため、趣味や教養、レジャーなどを楽しむゆとりある生活をするには、さらに約14万円必要ということになります。
お祝い金
子どものいる世帯では、子どもの結婚や新居購入、孫の誕生・進学など、子どもの自立後も親としての支出が必要になる場面があります。
なお、子どもの結婚費用は、100万円~200万円程度、出産祝いは、5万円~10万円程度は見ておくと良いでしょう。
リフォーム代
マイホームを所有している場合、ローン返済後も維持費は必要です。
老後を迎えるころには、30代の頃に購入したマイホームも老朽化が進んでおり、設備の交換などのリフォーム費用が必要になります。また、高齢になると体の自由が利かなくなりバリアフリー対策も必要になるでしょう。
戸建ての場合は年間40万円程度の維持費用が必要な他、急な修繕が必要なケースもあります。
できれば、いつでも使える住宅費用として200万円~300万円程度の貯蓄があると安心です。
医療費
高齢になると増加するのが入院・治療費と言った医療費です。
日本人の健康寿命は、女性が約75歳・男性約72歳で、平均寿命よりも10年程短い傾向にあります。
後期高齢者医療保険や高額医療費制度の利用により、ある程度医療費を抑えられますが、それでも若い時よりも医療のお世話になる頻度が上がる分、医療費の負担も増える可能性があるでしょう。
老後の医療費の負担を減らすためにも、早い段階で医療費保険などを検討して備えておくことも重要です。なお、70歳以上の高齢者の1回の入院費用の相場は20万円程度です。
介護費
厚生労働省調査の「令和元年度 介護保険事業状況報告」によると、75歳以上の方は全体の31.9%、約1/3の方が要支援・要介護の認定を受けています。
そして、生命保険文化センター「令和3年度生命保険に関する全国実態調査」によると、月の介護費の平均額は8.3万円。さらに最も回答数が多いのは15万以上となっています。
日本では介護保険制度により、介護サービスの利用者負担割合は料金の1割です。それでも、このような調査結果から介護費の負担はかなり重いことがわかります。
葬儀代
自分の死後に家族への負担を少しでも減らすために、葬儀代を準備しておく人が増えています。
一般財団法人の日本消費者協会の「葬儀についてのアンケート調査報告書(第11回)」によると、葬儀の平均費用は約196万円となっています。
しかし、葬儀の規模や地域によっても費用は異なるほか、返礼品・お墓の購入まで視野に入れるとより高額になる可能性があります。
近年では、「終活」という言葉が注目されており、エンディングノートなどに自身の死後の意向を残すことも多いです。
センシティブな問題ではありますが、家族に負担をかけないためにも、葬儀の方法やお墓の種類なども事前に話し合っておくと良いでしょう。
自分にとって必要な老後資金を貯める4つのステップ
老後資金を貯めるといってもやみくもに貯めようと思ってもうまくいきません。
自分にとって必要な老後資金を貯めるには、以下4つのステップを踏むのがおすすめです。

- 退職後の生活にいくら必要かを計算する
- 年金の受け取り額や退職金の額を把握する
- いつまでにいくら必要かを計算する
- 年間目標金額を設定する
それぞれどのようなことをするのか、具体的に解説します。
退職後の生活にいくら必要かを計算する
退職後に生活に必要な額は、世帯ごとに家族構成や収入・支出などの条件によって異なります。
まずは上述のモデルケースも参考にしながら以下のポイントを踏まえ、自分が老後生活するにはどれくらいの費用が必要なのかを計算しましょう。
- 老後の生活のイメージを具体的にする
- 老後のライフプランの作成
- 現在の支出の把握
老後の理想の生活をイメージしつつ、ライフプランの作成と現在どのようなことに・いくらお金がかかっているのかを把握すると、より具体的な老後の生活費を計算できるでしょう。
年金の受け取り額や退職金の額を把握する
老後資金の大部分は年金・退職金で賄えますが、不足額を確認するには、あらかじめ年金の受け取り額や退職金の見込み額を把握しておくことが重要です。
年金の受け取り額は、年金定期便やねんきんネットを活用することで大まかに把握できます。退職金の目安も会社の規定を調べると見通しが立てられるでしょう。
また、それ以外にも個人年金や保険の満期などで収入がある場合は、それらも老後資金として加えることを忘れず計算しましょう。
いつまでにいくら必要かを計算する
老後資金を蓄えるためには、どのような費用がいつまでに必要なのかを把握することも重要です。
- 住宅ローンの返済はいつまでに総額いくら必要か
- 子どもの教育資金は何歳までいくら必要か
- 家のリフォーム代や車の買い替えにいくらかかるか
- 旅行などの費用はどれくらい確保したいか
上記のような費用を考慮したうえで、老後資金を蓄えていくことが必要になります。
年間目標金額を設定する
必要な老後資金の目安がついたら、将来その目標金額が達成できるよう、年間の目標貯蓄額を設定します。
年間の目標貯蓄額は、老後必要資金を(年金受給年齢から現在の年齢を引いた値)で割ることで算出できます。
目標貯蓄額 = 老後必要資金 ÷ (年金受給年齢 – 現在の年齢)
たとえば、ともに40歳の夫婦の老後の必要資金が約2,300万円だとしましょう。その場合、上記の計算式に当てはめると、年間の目標貯蓄額は以下のように計算されます。
目標貯蓄額 = 2300万円 ÷ (65歳 – 40歳)= 92万円(月額約7万6000円)
したがって、この夫婦が今から老後の資金を準備し始める場合、その年間目標貯蓄額は約92万円。月額に換算すると約7万6000円になります。
老後資金のおすすめの貯め方【年代別】
老後資金を準備するにあたって、年代別で適した貯め方は異なります。ここでは、無理なく効率的に老後資金を貯められるおすすめの方法を年代ごとにご紹介します。

20代~30代の場合
若いうちは老後だけでなく、今後のキャリアアップや結婚・出産などあらゆる点を踏まえたライフプランの設計が必要になります。この段階から老後生活のことばかりを気にし過ぎているとライフプランニングがままならないだけでなく、貴重な若者としての時期を楽しむこともできません。
20代~30代までの場合は無理のない範囲で、月々または年間の目標額を設定のうえ少しずつ貯金を続けていくことをおすすめします。また、投資など資金形成に役立つ知識も勉強しておくとさらに良いでしょう。
40代~50代の場合
40代以降は、これからやってくる老後生活を意識し始める方が多いはずです。しかし子どもの教育費や住宅ローンの返済などの支出が続いていたり、ライフステージの変化により支出が増えたりと思うようにお金が貯まらないケースも珍しくありません。
この段階になったら自分に必要な資金は具体的にいくらなのかを計算し、無理なく貯蓄を続けていくと良いでしょう。また、貯蓄型の保険や投資など預金以外の手段も検討することをおすすめします。
60代以降の場合
60代になると、退職によりその後の収入が公的年金のみとなる方も多いです。自営業の方であればより長く働けることもありますが、加齢による体力の衰えやケガ・病気のリスクは年々高まります。
そのため、60代以降にお金を貯める場合は仕事による収入ではなく、投資信託やつみたてNISAなどを活用してお金を増やすことが大切です。
老後資金を貯める・増やす方法

老後資金は、年金だけでは不足する可能性が高いため、自分で効率よく蓄えていくことが重要です。
老後資金を準備するには、主に以下7つの方法があります。
- 退職金
- 定年後に働く
- 家計の支出を見直す
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 個人年金保険
- 財形年金貯蓄
- 新NISA(つみたて投資枠)
退職金
老後資金の大事な収入源である退職金ですが、退職金は年々減少している傾向があります。
従来の終身雇用制度から働き方も変わり、短期間で転職する人も増えています。また、そもそも退職金を設けていない会社も増えている点にも注意が必要です。
自分が定年まで勤めた場合に、いくら退職金がもらえるのかは事前に把握しておくようにしましょう。
定年後に働く
元気なうちは、定年後も働き続けることで老後資金の不足分をカバーできます。
定年後の働き方としては「再雇用」と「再就職」があります。
「再雇用」とは、働き方改革の一環として定められた「継続雇用制度」を利用する方法です。本人が希望すれば、定年後も同じ企業で引き続き雇用してもらうことができます。
一方、「再就職」とは、それまで勤めていた企業を退職し、新たに自分で仕事を探す方法です。
「再雇用」「再就職」はいずれも雇用形態が変わり、賃金も下がることが多いです。しかし、働き続けることは生きがいにもなるほか、健康の維持・増進にもつながります。
必要な老後資金に応じて、パート、契約社員、派遣社員などのなかから自分に合った雇用形態・働き方を選択すると良いでしょう。
家計の支出を見直す
老後資金を確保するためには、家計の支出を減らすのも有効です。
家計の支出を見直し、節約できそうな項目を確認してみましょう。
ただし、生活水準を変えると無理が生じやすいため、現状を維持しつつできるだけ無駄を減らす意識を持つことが大切です。
保険や通信費に関わる契約内容を変更したり、使用していない自動車を売却したりと、老後の生活に合わせた生活・予算の見直しをおこないましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
年金には、国民保険など誰もが加入しなければならない公的年金だけでなく、任意で加入できる私的年金もあります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、国が整備している私的年金制度です。
毎月決まった額を積み立てて運用することで、老後資金として備えられるほか、毎月の掛け金は所得控除の対象となる、運用益は非課税・受け取り時も控除が適用されるなど、税制上の優遇を受けられます。
ただし、iDeCoで積み立てた資金と運用益は、原則60歳まで受け取ることができません。
個人年金保険
民間の保険会社が販売する個人年金保険も、私的年金の一つです。
保険会社によって異なりますが、一般的には60歳や65歳まで一定期間保険料を積み立て、満期後に年金として積立金を受け取ることができます。公的年金の給付は65歳からのため、受け取り開始年齢をそれより前に設定すれば、年金給付までのつなぎとしても役立つでしょう。
個人年金保険の種類としては、確定・有期・終身の3つがあり、それぞれ年金を受け取れる期間が異なります。
確定年金は契約時に定めた一定期間、有期年金は契約者が生きている限り一定期間、終身年金は契約時に定めた年齢から死亡するまでの期間、それぞれ年金を受け取ることが可能です。
要件を満たすと所得控除が受けられるなど節税にもつながるため、各々のライフプランに合わせて選択すると良いでしょう。
財形年金貯蓄
財形年金貯蓄とは、国と会社が連携しておこなっている私的年金です。
毎月の給与から一定額が老後資金のための貯蓄として天引きされ、60歳以降5年以上の期間に年金として支払われます。
積立期間は5年以上で、マイホームの購入などを目的とする住宅財形貯蓄との合計額が550万円までは利子などが非課税になります。
給与からの自動引き落としで意識しなくても貯蓄ができるので、貯蓄が苦手な方にもおすすめです。
ただし、勤め先の会社が財形貯蓄制度を導入していなければ利用できません。
新NISA(つみたて投資枠)
新NISAとは、投資に対する国の税制優遇措置です。
つみたて投資枠では年間120万円の投資枠に対する利益が無期限で非課税となります。本来投資の利益には20.315%の税金が課せられるので、非課税になる分を再投資することで効率よく資産形成が狙えるでしょう。
新NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠がありますが、つみたて投資枠のほうが非課税投資枠が少なく、少額で始められます。
また投資商品は、長期積み立て・分散投資に適した一定の条件を満たした投資信託に限られているので、投資初心者の方はつみたてのほうが安心でしょう。
自宅を活用した資金調達方法もある
持ち家の場合は、上記以外にも自宅を活用して老後資金を調達することができます。
自宅を活用した主な資金調達方法は以下のとおりです。
- 自宅の売却
- リースバック
- リバースモーゲージ
- 不動産担保ローン
- 賃貸経営
自宅の売却
持ち家は資産価値が高いため、売却することでまとまった資金を得られます。
また、この方法は老後の暮らしに合った家に住み替えることができるのも一つのメリットです。
たとえば、子どもが独立して夫婦2人になったタイミングでコンパクトな物件に引っ越せば、家の管理が楽になるほか、光熱費の削減にもつながります。
その他バリアフリー設計や、徒歩圏内にスーパー・病院があるなど、生活利便性が高い物件に住むと、老後の生活が楽になるでしょう
リースバック
リースバックは、自宅を売却して賃貸物件として住み続ける方法です。
一般的な不動産売却では、自宅の売却後は退去することになります。しかし、リースバックでは家賃を支払うことで引き続き自宅に住み続けることが可能です。
売却したお金の使途は問われないため、老後資金だけでなく、目的に合わせてさまざまな用途にお金を使うことができます。
また、売却後は必要に応じて自宅の買い戻しができるのも魅力です。
リースバックについては、こちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください
[関連リンク]
リースバックの仕組みとは?メリット・デメリットや流れ、注意点をわかりやすく解説
リバースモーゲージ
リバースモーゲージは、自宅を担保に金融機関から融資を受ける方法です。
契約者は生存している間、借り入れ金の金利部分のみを返済し、死亡後、自宅を売却することで残債を返済します。
リバースモーゲージは基本的に、高齢者が老後の資金調達を目的として利用するローンです。このため金融機関によっても異なりますが、その資金使途は生活資金や医療費、住宅ローンの支払いなどに制限されます。
[関連リンク]
リバースモーゲージとは?やばい?仕組み・メリットなどをわかりやすく解説
不動産担保ローン
不動産担保ローンは、家や土地などの不動産を担保に金融機関から融資を受ける方法です。
持ち家の場合、家と土地の資産価値から借り入れの上限額が計算され、その範囲内で融資を受けることができます。
毎月元本の一部と利息を返済していく必要があることと、完済すれば持ち家のままでいられるのがリバースモーゲージと大きく異なる点です。
ただし、返済ができなくなった場合は、不動産を売却してローンの返済にあてる必要があります。
賃貸経営
持ち家を他人に貸して、家賃収入を得るというのも一つの手段です。
戸建て、マンションどちらでも住宅としてニーズがある立地なら、不動産会社に相談することで借り手を見つけられるでしょう。
ただし、賃貸経営をする場合は、自分たちが住む場所を考えなければなりません。賃貸経営による収入よりも家賃のほうが高いと、資金が徐々に減ってしまうため気を付けましょう。
老後資金に関するよくあるお悩みと対処法

老後資金を用意しようにも、自分はうまく資産形成をできる自信がないという方もいることでしょう。以下より、老後資金の用意に関して多く見受けられるお悩みとそれぞれの対処法をご紹介します。
①賃貸暮らしで将来が不安
老後も賃貸暮らしを選択するのであれば、老後資金は生活費だけでなく家賃も見据えた額を用意する必要があります。近年は高齢者に向けたバリアフリー化やサポート体制が整っている賃貸住宅も増えています。初期費用や賃料の相場をあらかじめ調査し、貯金額の目標を算出したうえで老後資金を用意しておきましょう。
賃貸暮らしを続ければ、家賃という支出は最後まで付いて回ります。少しでも無理なく家賃の支払いを継続できるよう、再雇用や投資など老後もお金を増やせる手段を検討しても良いでしょう。
②退職金制度が無い
退職金制度がない会社に勤めている方や自営業の方は、60代の貴重な収入源である「退職金制度」の恩恵を受けられません。
今後も退職金制度がない環境で仕事を続けていく場合は、「個人年金保険」や「個人型確定拠出年金(iDeco)」などを活用して自分で退職後の資金を形成する手段があります。退職金の金額は会社や業種などによって大きく変わりますが、一般的には1,000万~2,000万円程度です。それを踏まえて早いうちから資金形成を検討すると良いでしょう。
③貯金が苦手でなかなか貯められない
生活費が余るとつい消費してしまい、なかなかお金が貯まらないというタイプの方は珍しくありません。
前提として、貯金をする際は「生活費」と「貯金する分のお金」は別物として考えておく必要があります。あらかじめ生活費用の口座と貯金用の口座を分けておき、収入を得たらその月の支出を計算のうえ、先に貯金分を口座に入れておくと安定して貯金を続けられます。
また、「定期預金」や「個人年金保険」など、自動的にお金が引き落とされなおかつ簡単に引き出せない手段で貯金を行うことも1つの手です。
老後の資金に関するよくある質問
Q&A①老後資金はどのくらい確保できれば安心できるでしょうか?
A.ご家族の人数や暮らし方によって必要な金額は変わりますが、世帯の収入に応じて、公的年金だけでは足りない分は、貯蓄などで補わなければなりません。たとえば、毎月4万円を30年間貯蓄で補おうすると、合計で1440万円が必要になります。特に自営業者の場合は年金が少なく、退職金もないため、早めの資金計画が重要です。
Q&A②老後資金に回せるお金がない場合はどうすればよいでしょうか?
A.今からできることは、支出を抑えること、借金がある場合は債務の返済、副業などで収入を増やすことが挙げられます。長期的な視点からは、投資で資産を増やすことも選択肢の一つですが、投資はリスクが伴うため、自分のリスク許容度に合わせて適切な投資を選ぶことが大切です。またいざというときは、国の支援制度の利用を検討しましょう。
Q&A③そもそも老後とは何歳からを指しますか?
A.老後とは、一般的には定年退職後からその後の期間を指します。しかし、具体的な年齢については個人の意識によって異なります。なぜなら、一部の方々は定年退職後でも社会でさまざまな活動を続けているため、特定の年齢だけで「老後」と定義することは難しいからです。ちなみに、公益財団法人生命保険文化センターの調査では、老後資金を使い始める年齢について、平均で66.8歳というデータがあります。また、年齢の分布を見ると、65歳が一番多く、次いで70歳と60歳が続きます。
参考:
「老後」とはいつから?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター
まとめ
老後資金は、公的年金だけでは足りない可能性が高いため、自己の備えが重要です。
年金の受給額や老後に必要な資金を把握し、不足分はiDeCo(個人型確定拠出年金)などの私的年金をうまく活用してコツコツと蓄えることを心がけましょう。
また、持ち家がある場合は、自宅を売却し、その後賃貸として住み続けるリースバックや、持ち家を担保として金融機関から融資を受けるリバースモーゲージ・不動産担保ローンなども老後資金を蓄える資金調達方法の一つです。
それぞれの方法の特徴や違いを理解し、ゆとりのある老後を迎えられるよう、将来に向けて適切な選択をとりましょう。