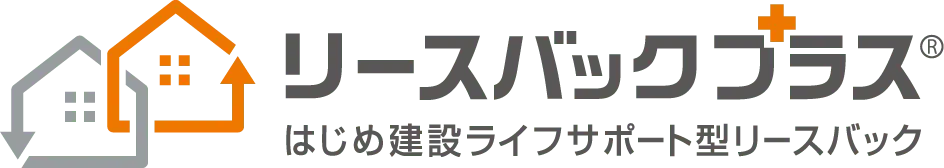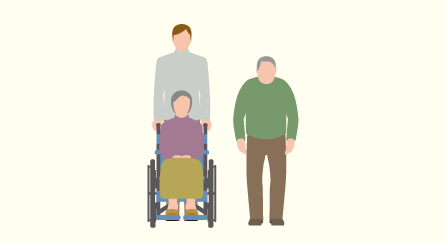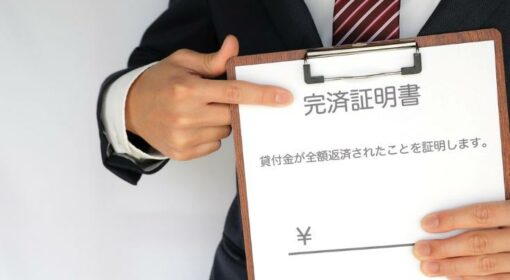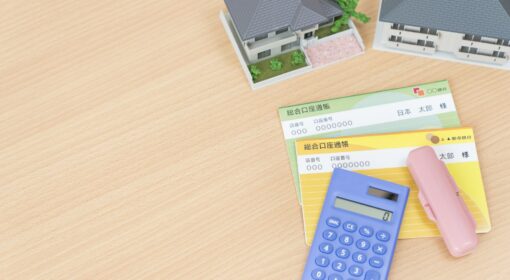最近、老後の資金調達方法として注目されている“リースバック”は、住宅の売買契約と賃貸借契約を組み合わせたサービスです。
リースバックの契約では、売買契約と賃貸借契約の2つの契約を交わしますが、契約時にはこれらの契約内容をしっかり確認しておかないと、思わぬトラブルに遭う可能性もあります。
今回は、リースバックの契約の流れや契約時に必要な準備、注意点などを解説します。
リースバックのメリット・デメリットについても本記事の後半で解説していますが、まずは、リースバックの仕組みについて詳しく知りたいという方は、以下の記事を参考にしてみてください。
INDEX
リースバックの契約の流れ
「リースバック」は、自宅を所有している人が資金を必要とするときに選ぶことができる、新しい資金調達の方法です。
リースバック契約の流れは以下のとおりです。

- リースバックを行っている不動産会社やリースバック専門業者に査定してもらう。
- 条件に納得がいったら、自宅を業者に売却する。(売買契約)
- 売却先の業者と賃貸契約を結ぶ。(賃貸借契約)
- 賃貸契約が有効なうちは、売却した住宅にそのまま住み続けられる。
リースバックには、利用にあたって査定や条件の調整といった審査が必要になります。リースバックの審査については、以下の記事で解説しているので参考にしてみてください。
[関連リンク]
ここからは、さらに詳しくリースバック契約の流れを解説します。
①リースバック業者の選定・相談・仮査定
まずは利用したいリースバック業者をピックアップし、希望の業者が見つかったら問い合わせをします。その際には多くの場合、物件の状況や希望買取価格などの条件を確認されます。
希望条件に問題がなければ「仮査定」の申し込みとなります。仮査定では、物件情報などをもとに大まかな買取価格と売却後の家賃が提示されます。
②現地調査・本査定
仮査定はあくまでも机上査定にすぎないため、実際に業者が自宅を訪問し調査する「現地調査」と「本査定」をおこなう必要があります。具体的な調査内容としては、物件の状態や図面との照合、境界線の確認などです。
仮査定では把握できなかった情報も踏まえ、現地調査と本査定後に買取価格や家賃が確定します。
③確定した契約条件の提示
物件の買取価格や家賃が確定したら、リースバック業者からその結果が通知されます。併せてさまざまな契約条件が提示されるため、内容をよく確認のうえ不明な点があったら小さなことでも業者へ確認しましょう。
なお、業者によっては買取価格や家賃は一定の範囲内であれば調整可能な場合もあります。
④契約
契約条件に問題がなければ、正式な契約手続きになります。契約を希望する旨を業者に伝えると、必要書類や契約日の日程確認が行われます。
リースバックの契約は基本的に、自宅を業者に売却する「売買契約」と売却先の業者と賃貸借契約を結ぶ「賃貸借契約」の2種類ですが、買い戻しを希望する場合は「再売買の予約契約」を交わすこともあります。売買契約や賃貸借契約に関しては、登記費用や印紙税、保証金などの費用も必要です。
⑤契約成立
契約手続きが完了すると、自宅の売却代金が支払われます。支払い後は売買と賃貸借契約が成立し、物件の所有権は業者側へ移転されます。
賃貸借契約によって定めた日から賃料の支払いが発生するため、この段階から毎月賃料を支払いながら自宅に住み続けることになります。
⑥買い戻し
買い戻しを希望する場合、「再売買の予約契約」で定めた期間後に自宅の買い戻しを行います。
買い戻しの期間・価格・買い戻しを行う人などの条件は、契約時に書面で記載された通りです。口約束だけで買い戻しを予約すると、後から条件を変更されたり買い戻しを断られたりするトラブルが起こりやすくなるため、必ず契約書に買い戻し条件を明記しておきましょう。
リースバックを利用するときに必要な契約書

リースバックの契約では、売買契約と賃貸借契約の2つの異なる種類の契約を同時に結ぶことになります。2つの契約内容どちらも問題ないか、よく確認する必要があります。
売買契約書
売り主と買い主が売買契約を結ぶ際に合意した内容を書面化したものです。
まず基本的なこととして、売買契約書では「売り主」と「買い主」を必ず確認しましょう。相談していた不動産会社が買い主だと思い込んでいたら、別会社や個人の不動産投資家が買い主ということもあります。買い主は賃貸借契約の貸主にもなるので、どのような相手かを知っておきましょう。
売り主に関しても、物件が家族などとの共有名義になっていないでしょうか。もしそうなら、全員分の署名や実印および印鑑証明書を用意しなければなりません。
また担保権を外すために住宅ローンなど借入金を完済する必要がありますが、その一括返済期限が金融機関などから設定されている場合、その前に現金が調達できるよう決済日についても注意が必要です。
売買契約書には以下のような内容が含まれます。合意した内容がすべて含まれているか確認しましょう。
- 契約者名
- 売買する不動産の面積や境界
- 売却価格、支払い方法や日程
- 手付金
- 所有権の登記(必要書類を揃える)
- 買い戻し可能か、買い戻し可能な期間や金額
- 設備の確認(故障の有無など)
- 固定資産税や火災保険料の清算
気になる売却価格ですが、リースバックでの売却は、一般的な売却よりも価格が低くなる傾向があります。しかもリースバックでは、必ずしも売却価格が高いほど良いとはいえません。必要な資金の額と、家賃、買い戻し価格のバランスを取った契約を結ぶのがベストです。
なぜなら、住み続けるときの家賃や将来的に買い戻すときの価格も、売却価格をもとにして決められるからです。売却価格が上がると、その後の家賃や買い戻し価格も上がることになります。
一方で、ローンが残っている場合、売却価格が残債よりも高くないと抵当権が抹消されません。そのため売却の査定価格が低過ぎると、リースバック契約自体が結べなくなってしまうのです。
また、いつ資金が入るのかも重要です。売却価格の記載に間違いがないかに加え、支払いの期日が自身の都合に合っているか確認してください。
さらに、買い戻しを予定している場合は、「買い戻し可能なのはいつまで」「買い戻し価格」といった条件を事前に話し合って、書面に残しておきましょう。
リースバックの価格に関してはこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。
[関連リンク]
リースバックの買取価格や家賃の相場は?再購入できるような金額?
価格以外の点でも、希望する条件は口約束ではなく必ず契約書に記載してもらうことで、のちのちのトラブルを避けられます。
リースバックでよくあるトラブルに関しては、こちらの記事で解説をしているので参考にしてみてください。
[関連リンク]
リースバックのトラブル事例11選 後悔や失敗をしないための対策を解説
賃貸借契約書
賃貸借契約で最も注意すべきポイントは、契約の種類です。リースバックでは、通常の「建物賃貸契約(普通借家契約)」ではなく、「定期賃貸借契約(定期借家契約)」となる場合がほとんどです。簡単に言うと、以下のような違いがあります。
普通賃貸借契約
基本的には、借主が借りたい期間だけ借りられる(更新できる)契約です。自動更新が原則で、借主の意向が尊重されます。貸主側から解約や契約更新の拒否をするには正当事由が必要となります。
定期賃貸借契約
定められた期間が過ぎたら契約は終了し(更新不可)、借主は退去しなければならない契約です。リースバック契約のほとんどは、2~3年の定期賃貸借契約になります。
将来買い戻す予定であるならば、この期間中に資金を用意しなければなりません。難しい場合は賃貸契約期間を長く設定してもらうか、再契約(または更新)可能という内容を契約に含めてもらう必要があるでしょう。
賃貸契約書には以下のような内容が含まれます。売買契約書よりも多くの項目があるはずなので、細部まで注意してください。
- 定期賃貸借契約と普通賃貸借契約のどちらか、何年契約か
- 賃料、敷金や礼金の金額
- 賃料の支払方法、支払先や期日(一括か、月毎かなど)
- 期間中の賃貸料の増減について
- 再契約(または更新)できるか、その際の費用
- 途中解約に関する規定
- 退去する際の原状回復(要不要や費用の負担)
- 設備故障時の費用負担
- 保証人
- 禁止事項(使用用途や、ペットに関する規定)
- 違約金
- 火災保険(建物に関する保険は通常所有者が負担)
- マンションの管理費・自治会費など(マンションの管理費・修繕積立金は通常所有者負担)
年間の家賃は売却価格のおよそ10%前後となっており、相場よりも高くなる傾向があります。のちに家賃の支払いのため家計が圧迫されないか、先を見越して計算してください。もともとの住宅ローンの支払いよりも毎月の家賃が高くなるようなら、再考の余地があるでしょう。
敷金や礼金は各社対応が分かれ、不要の場合や少なめになる場合もあります。
普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違い
| 普通賃貸借契約 | 定期賃貸借契約 | |
|---|---|---|
| 契約方法 | 書面・口頭どちらも可 | 書面(公正証書等)。※ |
| 契約期間 | 無制限(2000年3月1日以降の契約) | 無制限(契約で年数を設定) |
| 1年未満の契約 | 「期間の定めのない契約」とみなされる | 有効 |
| 期間満了後の更新 | 有(自動更新) | 無(期間満了により終了) |
| 借主が継続を望む場合の契約終了 | 貸主は正当な事由が必要 | 貸主は正当な事由は不要 |
※あらかじめ「更新がなく、期間の満了により契約を終了する」ことを契約書とは別に書面を交付して説明する必要あり。
ここでは提出のタイミング別に必要な書類をまとめましたので、直前になって慌てないよう目を通しておきましょう。
売買契約書の内容
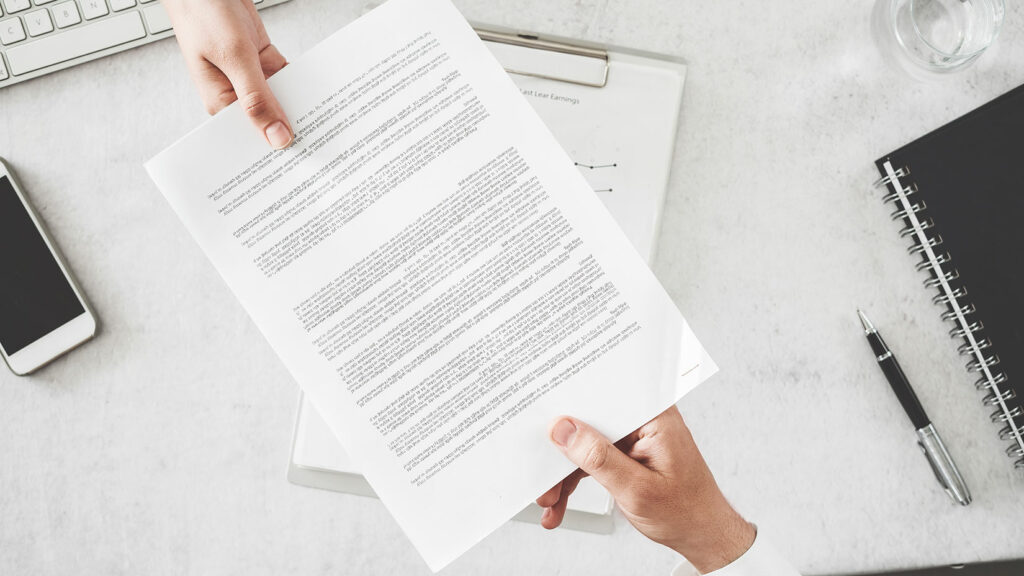
リースバックで物件の売買契約を締結する際に用いる、「売買契約書」の基本的な内容を詳しくご紹介します。
売買価格
規定の方法に基づいて算出された、物件の売買価格です。事前に合意した金額と相違がないかを、必ず確認しましょう。ごくまれではありますが、故意的に値上げした金額が記載されているケースもあります。
決済(引き渡し)の日程
資金調達を目的にリースバックを利用する方は、特に注意すべき項目です。事前の打ち合わせで資金が必要なタイミングに決済の日程を合わせている場合、しっかりと希望通りの日程が記載されているかを確認しましょう。
買い戻しの条件
将来的に買い戻しを検討している場合、事前に業者と「買い戻し期間」や「買い戻し価格」といった条件を取り決めたうえで売買契約書に記載する必要があります。口約束で買い戻しを予約しても、いざ買い戻すときに拒否されたり想定していた金額よりも高額な価格で買い取る事態に陥ったりしかねません。
賃貸借契約書の内容
売却した業者と賃貸借契約を締結するために用いる、「賃貸借契約書」の主な内容を詳しくご紹介します。

契約期間と家賃・敷金・礼金などの金額
賃貸借契約を締結するにあたって、契約書には契約期間の他に家賃や敷金などの金額が記載されます。これらの重要な情報が、事前の打ち合わせで取り決めた内容と一致しているかを確認しましょう。
なお、敷金や礼金の金額は家賃の1~2ヵ月分が相場です。場合によっては敷金・礼金なしで契約可能なこともあります。
賃貸借契約の種別
先述の通り、賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。契約の種別も契約書に記載されるため、確認しておきましょう。
家賃の支払い方法・期限
家賃の支払い方法は、毎月支払う場合もあれば一括支払いの場合もあります。家賃の滞納は買い戻しの権利を失う原因にもなるため、この先滞りなく支払いが可能な方法・期限であるかを確認しましょう。
また、契約期間中や更新時に想定外の家賃増額を求められると資金計画が崩れてしまいます。当初契約時に、家賃の増額についても取り決めをし、書面で残すとよいでしょう。
途中解約に関する取り決め
契約内容によって途中解約が可能かどうかは異なるため、途中解約をする可能性がある場合は事前に条件を取り決める必要があります。一般的な賃貸借契約では、途中解約は1~2ヵ月前までの申し出で認められるケースが多いです。
退去時の原状回復に関する取り決め
一般的な賃貸住宅は退去時に原状回復の義務がありますが、リースバック退去後は業者により物件が取り壊され、更地の状態で取引が行われることが多いため、リースバックでは原状回復が不要となる場合が多いです。
退去時に原状回復が必要かどうかを確認し、もしも原状回復が必要な場合、修繕すべき範囲や費用の自己負担分などを取り決め、その内容を契約書に記載しておきましょう。
リースバックの契約にあたって必要な書類
リースバック契約を結ぶにあたっては、複数の書類が必要になります。提出のタイミングは「本審査時」もしくは「契約時」で、書類によって異なります。
ここでは提出のタイミング別に必要な書類をまとめましたので、直前になって慌てないよう目を通しておきましょう。

本審査時に必要な書類
仮査定が終わったあとの現地調査・本審査時には、以下の書類が必要です。
- 本人確認書類(身分証明書)
- 住民票
- 固定資産税通知書
- 収入証明書
身分証明書には「運転免許証」「マイナンバーカード」「保険証」などが、収入証明書には「源泉徴収票」「年金通知書」などが該当します。
固定資産税通知書は毎年自治体から送付されます。お手元にない場合は自治体へ問い合わせてみましょう。
契約時に必要な書類
正式な契約手続きの際には、以下の書類が必要です。
- 印鑑証明書 ※発行後3ヵ月以内のもの
- 権利証
権利証には「登記識別情報通知」「登記済証」が該当します。
権利証は売買や相続によって自宅を取得したあと、登記を済ませることで法務局から交付されます。万が一紛失してしまっていても救済措置が設けられているため、焦らずリースバック業者に相談しましょう。
提出を求められる可能性がある書類
以下の書類は、業者によっては提出を求められる可能性があります。確認のうえ、必要であれば準備しておきましょう。
- ローン残高証明書、抵当権抹消書類
- 自宅の図面、土地測量図
- 掘削承諾書 ※前面の道路が私道の場合
- 重要事項説明書 ※戸建ての場合
- 建築確認通知書 ※戸建ての場合
- 境界確定書 ※戸建ての場合
- 管理規約、総会議事録 ※マンションの場合
リースバックの賃貸契約の期間
リースバックの賃貸契約期間は、契約の種類によって異なります。

「普通賃貸借契約」の場合、2年ごとの契約更新が一般的です。継続の意思を示したうえで再契約の手続きを済ませることで、契約期間満了後も契約更新できます。普通賃貸借契約では正当な事由を伴わない貸主の一方的な契約解除は認められないため、長く住み続けられます。
一方で「定期賃貸借契約」では契約期間が定められており、2〜5年程度で任意の期間が設定されます。契約期間満了後は貸主・借主のどちらも合意をすれば契約更新(再契約)が可能ですが、貸主が更新を断った場合は契約終了となり退去しなければなりません。貸主が契約更新を拒むための正当な理由は不要です。普通借家契約と間違えてしまうと突然住む場所がなくなってしまう恐れがあるため、契約の種類と契約期間はしっかりチェックしておきましょう。
そもそもリースバックとはどのような契約?

ここで改めて、リースバックの概要やメリット・デメリットを解説します。
リースバックとは
リースバックはセール(売買)&リース(賃貸借)バックと呼ばれることもあり、住宅の売買契約と賃貸借契約を組み合わせたサービスです。資金調達のために自宅など不動産を売却して所有権を移した後も、買主(貸主)にリース料(家賃)を支払ってそのまま住み続けられます。対象物件は一戸建てだけではなくマンションや店舗・工場なども利用可能です。
[関連リンク]
リースバックの仕組みとは?メリット・デメリットや流れ、注意点をわかりやすく解説
リースバックのメリットとデメリット
リースバックのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・引っ越しをする必要がない ・住居に対する税金や費用の負担が少なくなる ・将来的に買い戻す選択肢がある ・速やかな現金化が期待できる ・資金使途が自由 | ・売値が下がる傾向がある ・家賃が高くなるおそれがある |
リースバックのメリット・デメリットについては以下の記事も参考にしてください。
[関連リンク]
リースバックとは?仕組みやメリット・デメリット、トラブルの対処法をわかりやすく解説
リースバックがおすすめな方
メリット・デメリットを踏まえると、リースバックは以下のような方におすすめです。
- すぐにまとまった資金が欲しい
- 早く住宅ローンを完済したい
- 住宅の維持費負担を軽くしたい
- 老後にゆとりのある暮らしがしたい
- 相続問題を解決したい
リースバックは、上手に活用することで引っ越しをすることなく住宅ローンの返済や住宅の維持費負担、相続などのさまざまな悩み・問題を解決できます。特に、まとまった資金をすぐにでも手元に用意したい方におすすめです。
通常の不動産売却と異なり、手放した自宅にそのまま住み続けられるのもリースバックならではのメリット。のちに再購入もできるので、一時的に資金を確保するための方法としても有効です。
リースバックがおすすめな方は、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
[関連リンク]
リースバックはどんな人におすすめ?仕組みやメリット・デメリットも解説
リースバックを行う際のポイント

リースバックを有利に行うためにも、以下のポイントを意識しましょう。
資金の使い道は明確に決める
リースバックでまとまった資金を得ると、つい無駄遣いをしたくなってしまうのではないでしょうか。資金を得る手段としてリースバックを利用するなら、まずは「なぜ資金を調達するのか」「具体的にどんなことに資金を使うのか」といった、調達資金の目的・使い道を明確化しておきましょう。
資金の使い道と同時に、リースバック後の家賃は無理なく支払える金額となるかどうかも注意が必要です。
賃貸借契約の内容は必ずチェック
賃貸借契約書に記載されている、契約の種別・家賃の金額と支払期限・付帯条件・途中解約について・原状回復についてなどの内容は必ず目を通しましょう。よく確認しないまま契約を交わすと、後で想定以上に高い家賃を支払うことになったり、予期せぬタイミングで退去を迫られたりといったトラブルに発展しかねません。
売却価格の金額と根拠も要チェック
売買契約書に記載されている物件の売却価格も重要ですが、なぜこの価格で算出されたのかという「根拠」も確認しましょう。普通は市場価格や物件の条件・状態などを参考に算出されますが、少しでも違和感を覚えたら担当者に質問することをおすすめします。
特に売却して得た資金で住宅ローンを完済する必要がある場合は、売却価格が残債を下回らないよう注意しましょう。
買い戻しの検討
リースバック後に物件を買い戻したいと考えている場合、買い戻しまでの計画や対策を講じましょう。
「買い戻し特約」ならほぼ確実に買い戻せますが、売買予約による買い戻しは口約束だけだと買い戻しを拒否される可能性があります。そのため、契約の時点で買い戻しを検討している場合は契約書にも明記しておくと良いでしょう。
そのうえで、「いつ買い戻すのか」「資金をいつまでにどうやって用意するのか」など、資金調達の計画を立てます。
複数の業者を比較して選ぶ
リースバックを利用する業者を選ぶにあたって、複数の会社を比較しながら慎重に検討することをおすすめします。
選ぶ際は口コミだけでなく査定額の見積もりや付帯条件、地域の取引実績なども比較しましょう。適正な価格で物件を買い取り、負担が少ない家賃で賃貸借契約を結べる業者が理想的です。
[関連リンク]
リースバック業者の選び方を紹介!比較ポイントや失敗しないためのコツを解説
リースバックの契約に関するよくある質問
Q.リースバックの契約期間は?
A.リースバックの契約期間は、契約の種類によって変わります。
普通賃貸借契約は貸主側に正当な理由がない限り契約が更新でき、長期間住み続けることができますが、定期賃貸借契約は2〜3年で契約期間満了になる場合がほとんどです。
長期的に住みたい場合は、普通賃貸借契約で契約してくれるリースバック会社に売却しましょう。もしくは再契約が可能な定期賃貸借契約を選ぶのも手段の一つです。
[関連リンク]
リースバックはいつまで住める?契約期間や強制退去のケースを解説!
リースバック後はどのくらい住めるの?長く住むための方法をご紹介
Q.リースバックと賃貸の違いは?
A.賃貸はもともと他人が所有している住宅を借りて住む契約ですが、リースバックは自分が所有する住宅を不動産会社などに売却し、引き続き賃貸として住む契約です。
細かな違いとしては以下のようなものがあります。
- 原状回復義務が発生しないケースが多い
- 設備の修繕は借主負担
- 賃料は住宅の売却価格に左右される
- 契約後の賃料の交渉が難しい
- 住める期間が2〜3年と短いケースが多い
リースバックは相場ではなく売却価格を基準として賃料が決まるため、賃料が高くなりがちです。しかし、原状回復義務が発生しないケースが多いため、退去の際に思わぬ出費が発生することが少ないでしょう。
リースバックと賃貸の違いは以下の記事も参考にしてください。
[関連リンク]
リースバックを決めたら査定依頼をしよう!

リースバックでは、売買契約と賃貸契約という2つの契約を結ぶのでそれぞれの内容をよく理解・確認しましょう。売買契約では買主を、賃貸契約では契約の種類に特に注意してください。取引の過程に口頭で約束したこともきちんと記載されているか確認が必要です。
リースバックのメリット・デメリットを考慮したうえで実行すると決めたら、複数の会社へ査定を依頼し、取引する会社を決めます。
リースバックの商品の中で、他社にはない仕組みを取り入れ、様々なニーズに応えることができる3つのプランを用意している一建設株式会社の提供する「リースバックプラス+」をご紹介します。
売却後に賃貸契約を更新していくことが可能な「標準プラン」は、賃貸として住んだ長さに応じて再購入時の価格が下がる仕組みを、業界で初めて導入しています。最短でも10年間、再購入価格が下がっていきます。
一方、比較的早期の買い戻しを計画している方や一時的な資金調達の方には「定期プラン」が向いています。こちらのプランでは、最大1年間の賃料が0円(以降は定期期間に応じて賃料を設定)になる「賃料優遇タイプ」と、買戻価格が売却価格と同額となる(諸経費が別途かかります)「買戻優遇タイプ」があります。
標準プランでは、賃貸3年目以降は新築物件への引っ越しも可能という業界初の試みや、標準・定期の両プラン共通して、より快適で安心な生活のためのサポートサービスなども利用可能です。
このように、一建設株式会社の「リースバックプラス+」には、将来設計に合わせた充実のプランが用意されています。
リースバックをご利用になるなら、選べるプランと充実の特典が魅力の「リースバックプラス+」をご検討ください。